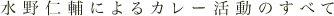あれはしない、これはしない。
あれはいやだ、これはださい。
なんのために僕は偏った美学で自分をがんじがらめにして生きているんだろう。誰も得しないというのに。
そう考えさせられる夜だった。
文春文庫から「カレーなる逆襲!」という小説が出版された。著者は、乾ルカさん。この小説を彼女が書き始めたのは、10年ほど前になる。僕はそのころ編集者の紹介で彼女と(確か札幌で)お会いし、カレーに関する話を色々とさせてもらった。その後、10年の間にほんの何回か、直接お会いしたり、編集者と話したりして、この小説の筋書きや内容にちょっぴりだけ協力させていただいた。
そんな本が、忘れたころに出版されることになった。出版社から献本された小説をこれから読むのを楽しみにしている。パラパラとめくっていたら、あとがきのページが目に留まった。見開き2ページの簡潔なあとがきの最後の2行に驚いた。
↓
***
最後に、カレーおよびスパイスについての取材において、様々なお話をお聞かせくださった水野仁輔様に、心より御礼申し上げます。
***
えええ!? 全く想像にない事態に少し動揺してしまう。あとがきの最後の最後をこんなことで締めくくっていいのだろうか。申し訳ない気持ちになる。
僕は、自分の本の中で、それがまえがきだろうがあとがきだろうが本文だろうが、「スタッフや関係者に対する謝辞は書かない」と決めている。またも面倒くさい美学のひとつである。
僕にとって本は作品である。作品は読者に向けられるべきものだ。その本の中で著者の僕が協力してくれたスタッフや関係者に向かっている姿勢を示すことはしたくない。スタッフや関係者は僕と同じ側に立って、一緒に読者と向き合ってもらいたい。だから、あとがきで常とう句のように繰り広げられる、「あなたがいなければこの本はできなかった」的な謝辞は、書くまいと貫いてきたのだ。50冊近くの著書でこの手のことを書いたことは一度もない。スタッフへ感謝の気持ちがあるのなら、それは内々に直接述べればいい。打ち上げで伝えたり、ダイレクトメールや会って「ありがとう、おつかれさま」と言えばいいじゃないか。
でも……。今回、乾さんの思わぬあとがきを読んだとき、「乾さんらしいな」とか、「粋だな」と思ってしまった。そうか、人にはそれぞれスタイルやスタンスがある。それをベースに動くことがその人らしさにつながるわけで、結果、僕はうれしい気持ちになっているのだから、謝辞を書くことはごく自然なことなのだろう。そうか、そういうこともあるんだな、と思った。とはいえ、僕は、これから先も自著の中でスタッフや関係者に謝辞を書くことはないだろう。ちっちゃなちっちゃな美学のひとつである。
ふう。
美学でがんじがらめにしたところで、僕は自分自身の美学が他人から理解してもらえるレベルのものではないと自覚している。誰かを楽にしたり、幸せにしたりするものでもないと自覚している。自分がどう見られたいのか、どう思われたいのかは気にしていない。自分が自分の存在や行為に納得して日々を過ごすために設定しているものが美学なのである。
だったら、僕は、誰ともつきあわず、独りで生きていけばいいじゃないか。マカオに行くのもポルトガルに行くのも、誰かに頼まれたわけじゃない。探求の末に何かアウトプットが待ち構えているわけでもない。リスボンの町中でレストランに入り、メニューに“Caril”を見つけてほくそ笑み、注文して食べながら、ふむふむこういう味わいならあれがこうなってこういうことになっているのかもな、なんて思いめぐらせて悦に入る。結果、誰も幸せにならない。
それならやっぱり独りで生きていけばいいじゃないか。
んんん、そういうことなのかもしれないなぁ。