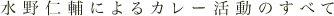蔦文庫刊行の辞
東京・日本橋室町に一軒の名のないカレー店があった。名がないのは正式な店名を誰も知らなかったからで、カレー好きの間ではずいぶん〝名の知れた〟存在だった。店の外壁には蔦がびっしりと絡まっていたから、「蔦カレーの店」と呼ばれていて、蔦の陰から「印度風カリーライス」と書かれた看板が控えめに顔を覗かせていた。中央通りに面した入り口の扉を開けて中に入ると、そこは大衆食堂という言葉がしっくりくる雰囲気だった。簡素な椅子とテーブルが無造作に置かれていて、主にサラリーマンが無心にスプーンを口に運んでいる。しゃばしゃばとしたカレーソースに豚のブロック肉が浮かび、ニンジンやジャガイモの塊と共に口に運ぶとヒリヒリと辛い。ひたすら素朴だが、なぜかご飯が進む味わいだった。客は一人残らずこの「印度風カリーライス」を頼んで食べた。なぜならこの店には他にメニューが存在しなかったから。多くのカレーファンから愛された「蔦カレー」の店は、二〇〇七年に六十年もの歴史に幕を下ろした。日本橋室町のあの一角には、今も人けのなくなった蔦の絡まる建物だけがポツリと残されている。
ここ数年、凛とした佇まいの老舗カレー店が、一軒ずつ姿を消している。何十年もの間、店主はカレーと向き合って生き、店に立って客を迎え続けてきた。その味わいには、弓矢が的のど真ん中を射抜くように「この味しかない」という切れの良さがある。メニュー構成もシンプルで、「これを食べてほしいんだ!」という店主の思いがハッキリしていて潔い。だからこそ閉店の知らせを耳にするのはたまらなく寂しく、例えようのない無力感に襲われる。それが世の常だ、と簡単に割り切ることは到底できない。長年の営業を通して培われた叡智は、今後、カレーの未来を歩んでいくための道標となるに違いない。この世には過去の遺産として遠ざけてしまってはならない存在があるのだ。
老舗のカレー店を称えよう。私たちはこの礼賛を永遠の事業として微力を傾倒し、あらゆる犠牲を忍んで今後永久に継続発展させていく。もってこの文庫に青々とした無数の蔦が絡まるその日まで、その使命を遺憾なく果たしたいと思う。
二〇一三年十一月
水野仁輔
蔦文庫 老舗カレー礼賛 刊行の辞
カテゴリー: 老舗カレー礼賛