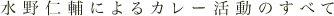宮城県の気仙沼へ行くとばかり思い込んでいた僕は、スタッフに連れられるがままに東北新幹線に乗って仙台へ行く。そこから在来線に乗り換えて1時間。到着したのは、福島県の相馬だった。
あれ? 今日は、気仙沼のさんま寄席だったはずでは……。今年は会場が変わったらしい。さんま寄席は例年通りのさんま寄席。立川志の輔さんが高座に上がり、僕は翌朝、朝市でさんまカレーを出すのである。
午前中から会場そばの調理場で仕込みに取り掛かり、おおかたを仕上げてから14時の開演に滑り込む。今年、志の輔さんを拝むのは、夏の「怪談 牡丹灯籠」以来2度目である。17時30分までになんと3席も! 「親の顔」、「ちりとてちん」、「柳田格之進」。どれもすばらしく、それぞれ枕でも大爆笑だった。
途中、司会進行の糸井さんとの対談で、矢野顕子さんがサプライズ登場。すごく意外だったのだけれど、志の輔さんは青春時代から矢野さんの大ファンで、すべてのアルバムを持っているそうだ。しかも、今日が初対面だそうで、嬉しさのあまりうろたえている姿を見た。僕にとっては志の輔さんがそれにあたる。面と向かったらうろたえるじゃ済まないだろう。
志の輔さんが、矢野さんに言った言葉が刺さった。
「舞台でお会いできて本当によかったです」
何の気なしに出てきた発言かもしれないが、僕は勝手にいたく共感した。舞台で会う。舞台で二人が会えるのは、プレーヤーどうしだからである。スタッフやファンは矢野さんと舞台の上で会うことはできない。志の輔さんほどの著名人なら憧れの人に会おうと思えばいくらでも紹介してもらえるだろう。でも、今日を迎えるまで彼は矢野さんには会わなかった。あったのは、舞台の上。「舞台の上で会えてよかったです」という気持ちは、会う理由ができたということだったんじゃないだろうか。
僕にも憧れの人はたくさんいる。いつか会いたい人はたくさんいる。たいていの人は数人を介せば会うことはできるだろう。でも、たとえ一方的に憧れている人であっても、理由もなく顔を合わせたいとは思わない。相手にとって何かしら“会う理由”ができるまでは、僕は誰にも会いたくないのだ。だから、「◎◎さん、紹介しますよ」という好意に対しては、いつも、申し訳ないと思いながらお断りしている。大事な人だからこそ、そんな風に会いたくない。
今日の僕にとっては、志の輔さんが、まさに会いたいけど会いたくない人だった。さんま寄席で1000人ものお客さんを全国から集めている志の輔さんのイベントで、隅っこの方でさんまカレーを作る自分。ものすごく希薄な関係で、志の輔さんにとっては、1ミリも会う理由のない存在である。
高座に上がっている志の輔さんを僕は最後列から3つ前の関係者席に座って見つめ、あまりの眩しさに目がチカチカするような気持ちで3時間30分を過ごした。これで数か月は元気に頑張っていけそうだ。これでいい。生で見れただけで本当に幸せだと思った。
高座の後、場所を変えて観客の方々も交えた壮大なイベントが始まった。その間も会場の中心に志の輔さんはいた。無理やり近寄って行けばいつでも声をかけられる。でも、僕は、決して近づくまいと会場の外に出て日本酒をチビチビ飲みながら、ぼーっと過ごした。イベントが終わり、ほぼ日のスタッフが、「ラーメンでも行きますか?」と声をかけてくれたので、ついていく。
スタッフだけで15人くらいのこじんまりとした打上げである。ラーメン店の中に入ると……、そこに志の輔さんがいた。うそ……? 驚く間もなく、隣にいた糸井さんが僕を紹介してくれる。
「この人、カレーの水野さん」
僕は一気に舞い上がってしまい、ちょっとしどろもどろになりながら、挨拶。
「あの、その昔、ためしてガッテンでカレー特集したときに出演させていただいて、お世話になりました」
「どうもどうも」
志の輔さんは、「そうか、じゃあ、そのときに会ってるんですね」くらいのライトなリアクションで握手の手を差し伸べてくれた。握手を交わし、僕は逃げるようにラーメン店のカウンターに腰かけた。理由が見つかるまで会いたくないだなんて考えを持っていたのはどこのどいつだ! 紹介されて舞い上がり、握手までしてしまったではないか。ちょっと自己嫌悪に陥り、ラーメンをすする。
3つ隣りに志の輔さんがいる。僕は、まだ軽い緊張がとけず、動揺して、スマホを手に取った。毎年「怪談 牡丹灯籠」に連れて行ってくれる友達の編集者にメールする。
「志の輔さんに挨拶してしまいました。どうしよう。近くにいるけど恐れ多くて近寄れません」
僕よりはるかに筋金入りの志の輔ファンである彼女は、メールの文面だけで僕以上に興奮してしまったようだった。
「わわー。でもきっと恐れ多がられ慣れてますよ! ここはひとつ話しかけてみては!? なーんて。自分ならできないかなぁ」
スマホを置いて、しばらく、スタッフと話しながら気を落ち着かせる。僕は舞台の上で会うまで志の輔さんとは会いたくない。でも、会いたい。いや、会ってはいる。話をしたい。やっぱり話したくない。志の輔さんの隣りには糸井さんがいて、楽しそうにふたりで話している。もちろん、それ以外にラーメン店にいる誰もがそこへ近づこうとはしていなかった。
僕が勝手にドキドキしていることを除けば、ひとしきり、会は和やかに進み、早々にお開きになった。スタッフはテキパキと身支度をして、一人二人と店を出ていく。奥では志の輔さんと糸井さんが取り残されるように話している。
僕は席を立って、彼らに近寄った。ひとまず、志の輔さんの元へ行ってみようと思ったのだ。言いたいことはひとつだけ。シンプルにそれを伝えて帰ろう、と。恐れ多い気持ちで近づく僕を見て、やっぱりそんなことには慣れっこだからなのか、志の輔さんは僕がしゃべり出す前に笑顔で目を合わせてくれた。
「あの、去年と今年、牡丹灯籠を観させていただきました」
「ああ、そうですか! ありがとうございます」
「去年、初めて観たときは、あまりの衝撃に翌日までボーッとしてしまいました」
「いやいや、ありがとう。毎年同じ噺を演り続けるのがどんだけ大変か」
そう言って志の輔さんは隣りに座っている糸井さんの背中を思いっきりたたいた。
「いやね、本当に大変なんですよ」
小さく頷いていた糸井さんがひと言。
「ま、水野君も毎回同じカレーを作ってるからねぇ」
「カレーね、カレーはいいですよ。煮込めば煮込むほどおいしくなるから。でもね、牡丹灯籠は煮込めば煮込むほどおいしくなるかどうか……」
そう言って志の輔さんはとても嬉しそうに笑って続けた。
「下北沢本田劇場の支配人がね、牡丹灯籠を毎年続けてるって言ったって、たかだか2万人か3万人しか観てないんだから、ずっと続けなきゃって発破をかけるからね」
もう僕はお腹いっぱいだった。これ以上この場にいたら、倒れてしまう。すっと席に戻って身支度をし、店を出てスマホを取り出した。友達に報告する。
「しゃ、しゃべりました!」
と、僕がメールを送る前に彼女からはそれこそ僕に発破をかける内容がすでに届いていた。
「そういうときは、何も考えずに、立ち上がって近くまで行くと、後に引けなくなって事態が転がり出しますよー。かけにくい電話のときに、とりあえず考えずにダイヤル回すのと同じです」
たしかに今日の僕は、考えずにダイヤルを回せたのである。短いけれど幸せなひとときだった。次に会うときまでには志の輔さんにとって会う理由のある存在になっていたい。ひとまず今日の段階では、「志の輔さんに会いたいけれど会いたくない問題」については解決したと言えるだろう。
頭の中で今日聞いた「柳田格之進」の“下げ”が、志の輔さんの低い声で鳴り響いた。
「たった今、いちばん大きな白い黒いがつきました」